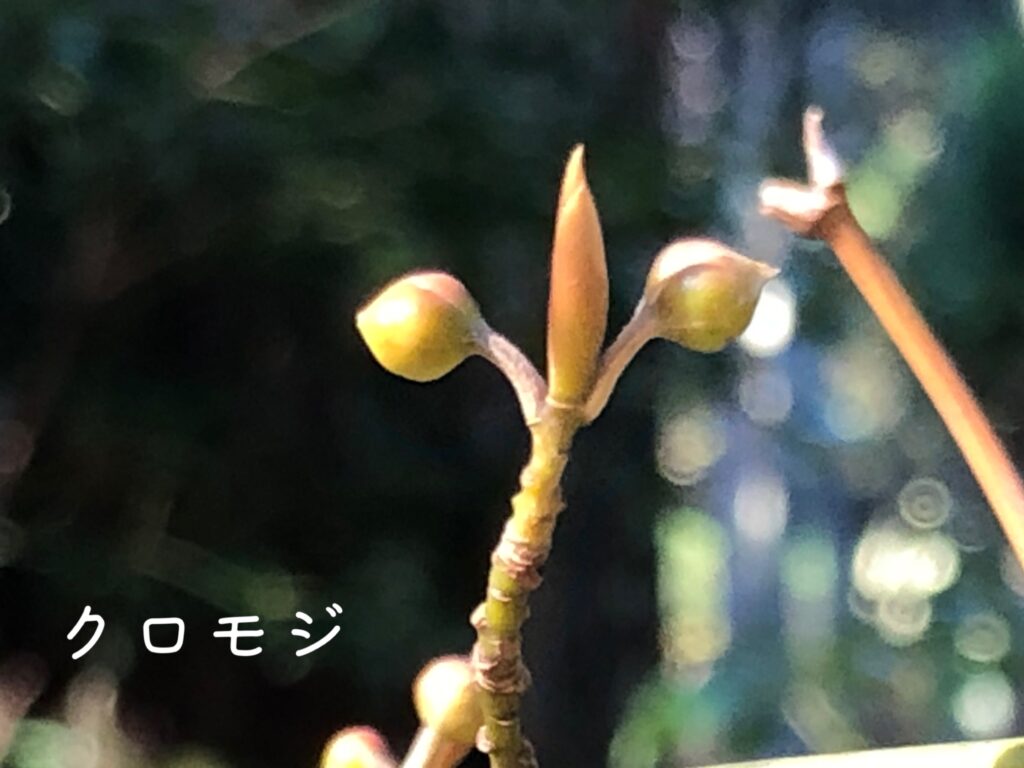研修の概要
- 研修の目的:
会員から要望のあった症例、および、あるある症例をもとに、普段のガイド活動において実践的で役立つ、予防方法、および、早期発見・早期対応方法を学ぶ。 - 開催日時:2024年6月30日(日) 9:30~15:40
- 場所:アイプラザ豊橋
- 参加人数:13名
研修内容
ガイドは、安全管理を徹底的に!傷病者を出さないための予防法、早期発見、早期対応。でも、具体的にはどうやって?
参加者からの事前リクエスト内容も含む、実際の症例、7症例+αをもとに、その場に居合わせた時に、ガイドとしてどのような行動をとったらよいか?
1つ1つの症例に関して、観察ポイントや、どんな声かけをして正確な情報を引き出すのか、本人からの主観的な訴えだけではなく、客観的な評価方法、考え方のプロセスについて、参加者全員で意見を出し合い、考え抜きました。

外傷性の怪我は視覚で確認できることが多く対応しやすい。一方、内因性の疾患のことは、わかりにくい。だからこそ、参加者全員で可能性のあるいくつもの要因を探し出してみました。実際に、要因は1つだけでなく複数ある場合も多いです。複数の要因から、さらに情報を正確に得ることによって消去法で絞り出していきます。そして、これから起こり得ることの予測をして具体的な早期対応、予防をはかっていくことが重要です。
白熱した意見交換の後は、どうしてそのような症状が起こったのか、登山ガイド&DIMM山岳看護師でもある講師から根拠となる医学的視点における病態生理、メカニズムについて説明がありました。

メカニズムを理解した上で、会員から似たような症例の経験談を語ってもらいました。会員間でお互いに情報共有することで、さらに理解を深めることができます。会員ひとりひとりの経験談こそが、どう声かけするか、ガイドとしての役割、予防方法は?今後の登山行動計画は?ガイド視点で考え、あした。

夏山本番に向けて、脱水、熱中症対策は欠かせないです。
経口補水液あれこれ。市販のものもあるけれど、どの家庭にもあるものでお手軽に手作りできます。顧客が真水しか持っていない時は、どう対応する?顧客が持ってきているものを有効活用!飲み比べ、試飲してみました。
あるある症例に対して、それぞれのガイド達の予防を含めたオススメ対応グッズ!
これこそフィールドで役立つグッズの紹介あれこれ!

かぼすジュースレシピ



その他、こちらにアップ仕切れない数々のグッズに講師も写真を撮りまくりでした(笑)
本格的な夏山シーズン前に、参加者全員で真剣に考え意見交換、情報共有。
まさに、フィールドで役立つ実践的な内容の確認ができた研修会でした。